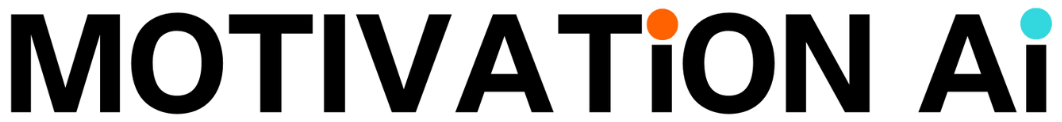MAIのビジョン|大人のAI教室 MOTIVATiONAi
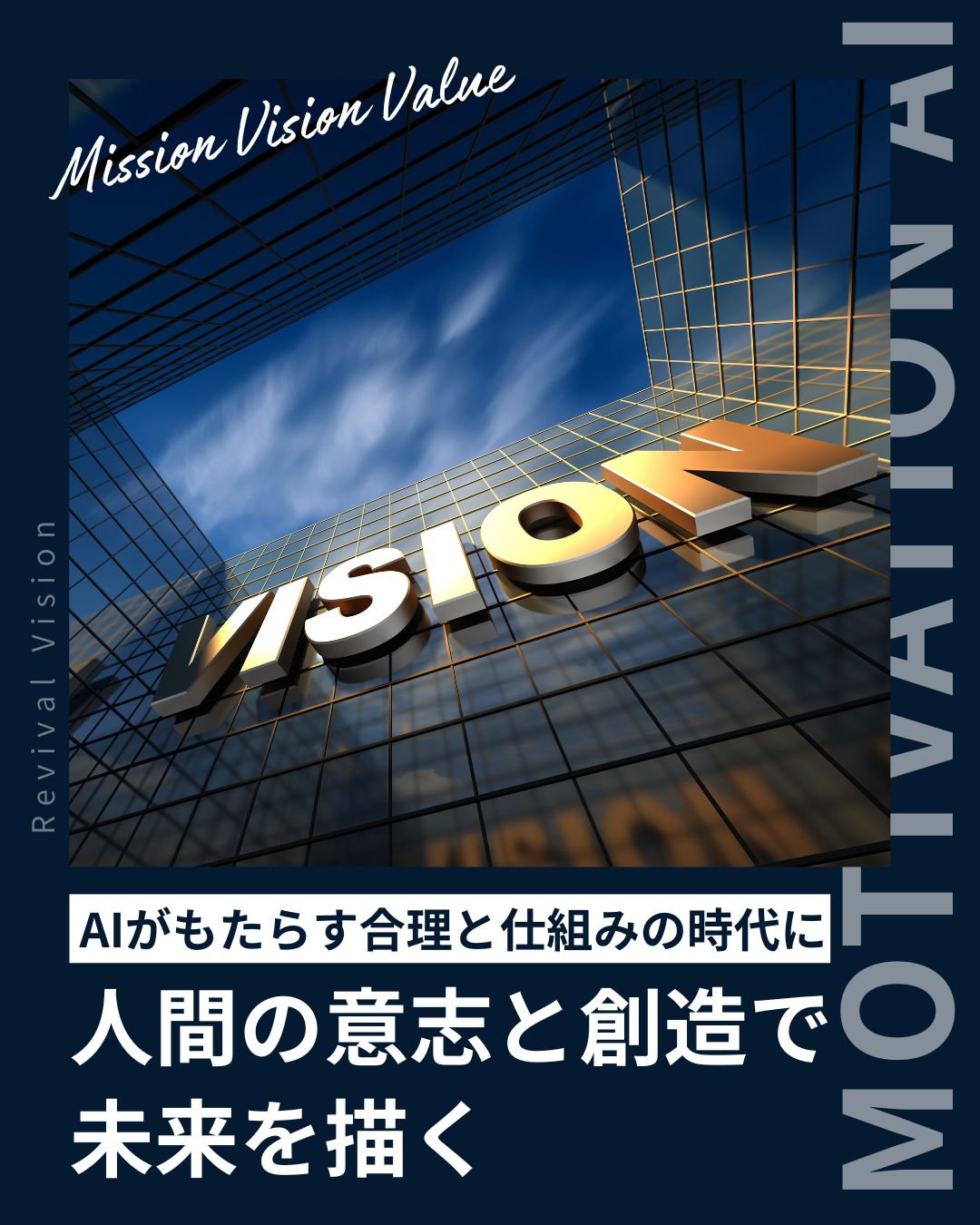
合理的な予測の時代に、未来を描く創造力を
AIが多くの答えを用意し、あらゆる判断が最適化されていく社会では「努力する理由」や「未来への挑戦」が見失われがちです。私たちのビジョンは明確です。AIの合理が前提となる時代にあっても、人が自らの意志で望む在り方を描き、希望と愛を携えて力強く歩む世界をつくること。未来は当てるものではなく、人間が願い、望み、描き、創るものであると信じます。MAIは、AIが前提となる新しい時代にあって、人間が希望をもって未来を描き出す力を養う教育文化の創造を目指します。
ミッション
生成AIが合理と予測で多くの「答え」を用意する時代に、私たちは「意志」と「希望」と「愛」を携え、自分たちの未来を自分たちで描き直します。MAI(MotivationAI)は、スキルとしてのAI習得にとどまらず、人間とはなにかについて問い。教育・仕事・文化をAIを前提とする新しい時代のものへとアップデートします。そして個人と組織が日常の実践を通じてその力を獲得することができるようプロブラムを設計・提供します。
なぜ今、MAIが必要か
2023年に大規模言語モデルが社会実装され、AIは一気に身近な道具になりました。しかし、この生成AIの普及と発展の速度に人間の変化が追いついているとは言えません。使い方を覚えることはできても、考え方・習慣・倫理をAI時代に適合させることは容易ではなく、情報が行き渡るほど、手段が誇大化し、目的や意味が曖昧になる場面も増えています。便利さが増す一方で、何のために学び、働き、創造するのかが見えにくい―そのギャップこそが私たちの出発点です。
MAIは、AIを「使えるかどうか」だけではなく、「AIを前提に人がどう在るか」を主題に据えます。知識の配布に留まらず、行動と文化を変え、社会に定着させていく。私たちはそのための言語と方法を磨き、具体の現場に持ち込み、検証し、共有します。
私たちの宣言
使命
人間がAIに従属するのではなく、AIと共に「意志で未来を描く力」を取り戻します。目の前の課題を素早く解くことだけで満足せず、どのような社会を望み、何を大切にし、どのように他者と協働するか――その設計までを全ての人に描いていただけるよう、私たちは自らのあらゆる活動において示し、伝え続けます。
目指す世界
AIという予測と合理の時代にあっても、人が自らの創造性によって希望ある未来を描き、力強く、愛とビジョンをもって生きる。未来は「当てるもの」ではなく「描くもの」だと信じ、AIを横に置きながら、自分たちの望む在り方を実現できる社会を目指します。
挑戦
不確実で、不安定な「未来へビジョンをもって飛び込むこと」を合理的な行為として、再定義し、教育として具体化します。予測が豊かな時代に必要なのは、予測に従う技術ではなく、意味を設計する意志です。
MAIを貫く五つの原則
Ⅰ.AIの一般化は、知識ではなく人の変容である。
AIを広げるとは、ツールの操作方法を配ることではありません。考え方、習慣、倫理をAI時代仕様に書き換え、AIがそばにいる前提で判断し、行動し、協働できる状態へと自分を作り変えることです。私たちは「知る」「使う」を通過点に、「前提にする」という到達点まで伴走します。そのために、まずMAIの内側を実験共同体とし、体現された型を社会へ開きます。
Ⅱ.AIと人間は、代替ではなく共進化する。
AIは合理を、人は意味を担います。情報の収集や最適化はAIが得意でも、何を目指すかの決定や関係の形成、責任の引き受けは人の領域です。役割を明確にし、互いの強みを尊重する設計によって、AIと人はともに成長できます。私たちは、この「役割の設計」を学びの中心に置きます。
Ⅲ.希望は、感情ではなく設計である。
明確な目標、組み立てられた日々の行動、定期的なふりかえりと改善という構造がそろったとき、希望は再現可能な力に変わります。MAIはAIを伴走者として、自己理解を深め、望む未来像を言語化し、行動に落とし、記録から学び直すサイクルを設計します。
Ⅳ.経営とは、効率ではなく意味を拡張する営みである。
組織は単に成果を出す機械ではありません。AIで効率を高めながら、人が方向と文化を決める。意思決定の可視化、倫理的な自動化、全体最適の視点を通して、経営を「合理×意味」の両輪で再設計します。私たちの研修は、現場で機能する原則とプロトコルに落とし込みます。
Ⅴ.愛は、時代を超越する教育の根拠である。
AIは知を支えますが、関係は人が育てます。相手を愛し、時間をかけて関わり続ける在り方こそ、教育の中心に据えるべきものです。私たちは、AI(知・論理)と人(共感・存在)を両方見せる「二重焦点」の設計で、温度のある学びを実現します。
成果からはじめ、未来へ繋ぐ
私たちはまず、成果に集中します。AIによって売上や利益、品質、速度、創造性といった現実の指標に変化を起こすことを最優先に据え、ビジネスや教育、医療、行政、クリエイティブなど多様な現場で結果を出すことに集中的に取り組みます。机上での理解ではなく、実務の文脈で機能するプロンプト、評価、検証、合意、記録までを含むプロトコルとして運用し、同じ手順で再現できる形に整えます。
そして、結果だけで終わりません。達成した成果を「原理」と「方法」に還元し、今日に役立つ実務から明日を見通す設計へ橋をかけます。シナリオ・プランニングと社会潮流の観察を重ね、ケースから学んだ知見を原則へ、原則を再び現場の型へと循環させる。この「成果 → 原理 → 方法 → 文化」の循環が、MAIの学びを一過性の流行から、更新し続ける実装知へと育てます。
大人が飛び込み、次の世代へ橋をかける
私たちは、AIが普及した時代における子どもたちの教育について、完成された答えを持っているわけではありません。だからこそ、まず大人である私たち自身がAIに飛び込み、試し、間違え、言語化しながら、何を学び直し、どのように働き、どう関わるべきかを探求します。その過程で立ち現れる知恵を、子どもたちに渡せる形に整えること——それが今のMAIの中心です。
個人には、ゼロから安全に成果へつなげる実装型の学びを提供し、学ぶ人が教える側に回れるよう教授法と評価、倫理とケース開発を備えた育成を進めます。組織には、業務の再設計から意思決定の可視化、文化づくりまでを伴走し、AIが合理を、人が意味を担う体制への移行を手伝います。そして、先の世代から受け継いできた「人間としての核(勤勉さ、責任、他者への敬意、約束を守る姿勢)」を、AI時代の現実に通用する実践へ翻訳し、次の世代へ橋をかけます。
子どもたちに向けては、拙速に正解を示すのではなく、大人が模索した結果を「温度のある学び」として差し出します。AIから知を学び、人から関係と愛を学ぶ二重焦点の設計を守りつつ、彼らが自分の言葉で未来を描けるよう、予見の地図ではなく「描き方そのもの」を渡していきます。
学びたい個人も、教える立場の方も、組織の変革に挑む皆さまも——MAIは開かれた学びの共同体です。私たちはAIの合理を活かしながら、人間の意志・希望・愛を中心に据え、実装と連帯で社会を前へ動かします。名古屋から日本へ、そして世界へ。あなたの参加と対話が、次の一歩を具体にします。